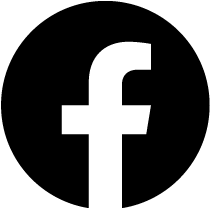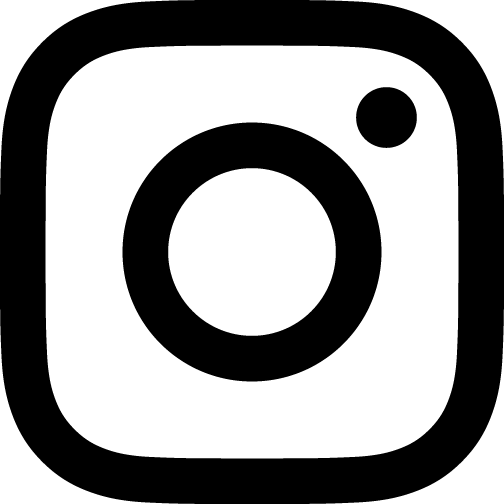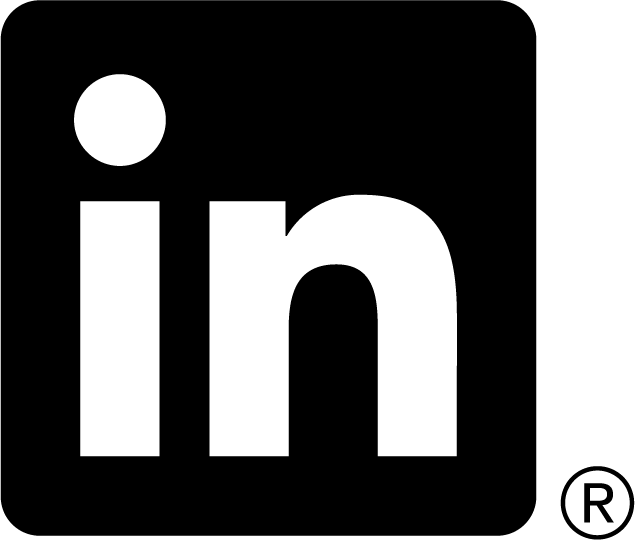- JP
- EN
社長
メッセージ
「成長と安定経営の両立」
それが私の使命です。
強いものをより強く
商船三井グループ経営計画
「BLUE ACTION 2035」
Phase 1の総仕上げへ

代表取締役 社長執行役員
本メッセージは、統合報告書「MOLレポート2025」
からご紹介しています。
当社グループが目指す事業ポートフォリオに向けた基盤が整備されたPhase 1(2023-2025年度)

事業全体のポートフォリオ変革は「BLUE ACTION 2035」で掲げる目標の要です。典型的な市況産業である海運業を事業基盤として発展してきた当社グループは、海運市況の波がある中で、業績や株価が安定しづらい状況が続いていました。確実に成長を続け、安定的に株主の皆様へ還元するためには、市況に左右されづらい事業ポートフォリオへ変えることが最重要課題です。これまでの2年間で、当初の計画を上回るスピードで投資が進捗し、2035年に当社グループが目指す事業ポートフォリオに向けて着実に事業基盤が整備されています。
具体的には、従来型の市況変動性の強い海運業とは異なる非海運の比率を高めるため、海洋事業や不動産事業、クルーズ船事業への投資を実施しました。2025年6月には、ケミカルロジスティクス事業の強化を目的に、欧州および米国でケミカルを中心に取扱う大手タンクターミナル会社であるLBC Tank Terminals Group Holding Netherlands Coöperatief U.A.の100%持分を取得し、子会社化しました。また、もう一つの重要なテーマである脱炭素の取り組みに向け、洋上風力発電事業や今後の代替燃料の要になると考えられるアンモニアやメタノールといった上流プロジェクトへの投資を拡大してきました。
しかし、投資の進捗に伴い、様々な課題も浮上しています。特に新規事業や、海外で地域に根差した事業を進めていく中では、従来の組織では十分にビジネスを進展させることが難しくなっています。収益性を高め、成長を持続させるためには、単に投資を続けるだけでは前に進めない局面に差しかかっており、組織や人財の強化により足腰を強くしなければならないという課題感を強く持っています。アセットを買うだけでは成功しませんので、いかに稼げるような事業構造をつくり上げていくかが、これからの大きなチャレンジです。そのためにも、2026年度より開始するPhase 2では、相当な力を注いで組織や人財を育て上げることが重要なテーマです。
ビジョン実現の要諦は人財にほかならない
「安定」と「成長」を両立させるには、ある程度時間を要することは初めから覚悟していました。これまでの投資によって事業基盤を構築し、さらなる成長の機会を確保することができました。経営計画は着実に進捗していますので、Phase1で掲げた目標は突破できていると評価しています。
事業構造の変革を遂行する中では、そのステージにより、異なるタイプの人財が必要となります。「BLUE ACTION 2035」の開始当初は、従来型の発想にとらわれず自ら新しい事業を切り拓き、その地域で活躍できる人財が必要であり、様々な分野で先頭を走れる人財が何名も現れ、事業の領域を広げてくれました。しかし、次のステージでは、立ち上げた事業の収益化に向けて、組織や仕組みを構築できる経営人財を育て、事業の現場に送り込んでいかなくてはなりません。単に事業を運営できるだけでなく、高度な専門性と、その地域における知識・経験やコミュニケーション能力の高さを兼ね備えていることが理想です。そうなると現実問題としては、本社の人財だけではなく、当社グループの多様な地域や拠点の人財の活躍がなければ、本当の意味でグローバルに事業を成功させることは叶いません。したがって、当社グループの各地域や拠点の人財のモチベーションを高め、エンゲージメントレベルを上げていくことも大きな課題です。
各国でビジネスを成長させていくには、その国でビジネス経験を積み、ネットワークや人脈、様々な知見を有する人財を集め、彼らが持っている潜在力を十分に発揮してもらうことが必要であると強く感じます。産業構造や事業環境は目まぐるしく変わっていますので、既存の成功体験にとらわれず、その国を熟知している人財が、伸び代のある分野へ大きく舵を切る、または事業を売却して他の部門に投資をするというような経営判断ができれば、その国で長期的に収益力を高められるはずです。そのため、2025年度より導入した新人事制度では、専門人財の定義を明確にするとともに、高い能力や実績に報いるという制度へと変更しました。世界で勝負できる専門人財が集まる組織への変革を制度面でも後押しします。
私の実感としては、商船三井グループにおいて人財の伸び代が大きいのは、各地域や拠点で活躍する人財と女性であると感じています。日本は国全体として女性活躍が進んでおらず、少なくとも女性の役員や上級管理職が全体の3割を占める程度にまでは推し進める必要があると考えます。私たちもいずれ、DE&Iと真の能力主義という2つのアジェンダとどのように折り合いをつけるかは問われると思います。しかし、何よりも重要なことは、当社グループに集う多様な人財が持つポテンシャルを解き放つということです。本来100のポテンシャルを持つ人が、半分の力しか出せていない状況があるとすると、残りの50を引き出すことができれば、人数を増やさなくても全体のパフォーマンスが向上するわけです。そういった社員一人ひとりのポテンシャルを十分に発揮できるグループにしていきたいと考えています。
変化する世界経済に地域密着型の戦略で挑む

世界経済の大きな潮流の一つは、これまで私たちが大いに享受してきたグローバリゼーションに逆風が吹いているということです。米国を例に挙げると、今までよりもブロック経済化が進んでいると考えます。各地域社会を上手に運営することと、グローバルエコノミーでの最適解を追求することは、必ずしも一致しなくなってきている現実があります。私たちとしても、従前のように世界の経済や貿易が順調に成長を続ければ、事業が安泰だという楽観的な見方はしづらくなっています。したがって、世界各国の経済がどういう段階で、どういった需要があり、それに対して最適な事業は何かをきめ細かく分析しながら、物流を始めとする地域のニーズを掘り起こして、競争優位なポジションを確保していきたいと考えています。
ブロック経済へと変化しているのだと考えると、地域密着型で地域のニーズを掘り起こしビジネスを組み立てていく必要を感じます。そうした中で、地域戦略において海運業だけでなく、倉庫事業、不動産事業や脱炭素事業といった分野にも取り組むことには大いに意味があると思います。事業を通してその地域の経済をより深く理解し、ネットワークを張り巡らせて現地のパートナーと新しいビジネスを行うというミクロなアプローチは非常に重要となるためです。
一方で、世界全体の潮流は、米国、中国、ヨーロッパなどがお互いにどういった関係性を持って政策を決定するかが大きく影響します。各国・地域の関係性は20年前とは全く様相が異なっており、そこにインドといった新しいビッグプレーヤーも加わってきますので、インテリジェンスが重要です。1つの対応策として2025年6月に、ワシントンD.C.に新たに拠点を設けました。すでに拠点を構える東京やロンドン等にワシントンを加え、地球全体を見渡してマクロな政治・経済状況と、各地域のミクロな状況がどのように結びついているかを分析することが本社機能の重要なポイントになります。今後は、本社から各地域組織に対して分析に基づいた適切なガイダンスを出し、より地域との連携を図りたいと考えています。
Phase2に向けて勝ち筋を見極めて事業の進退を決断する
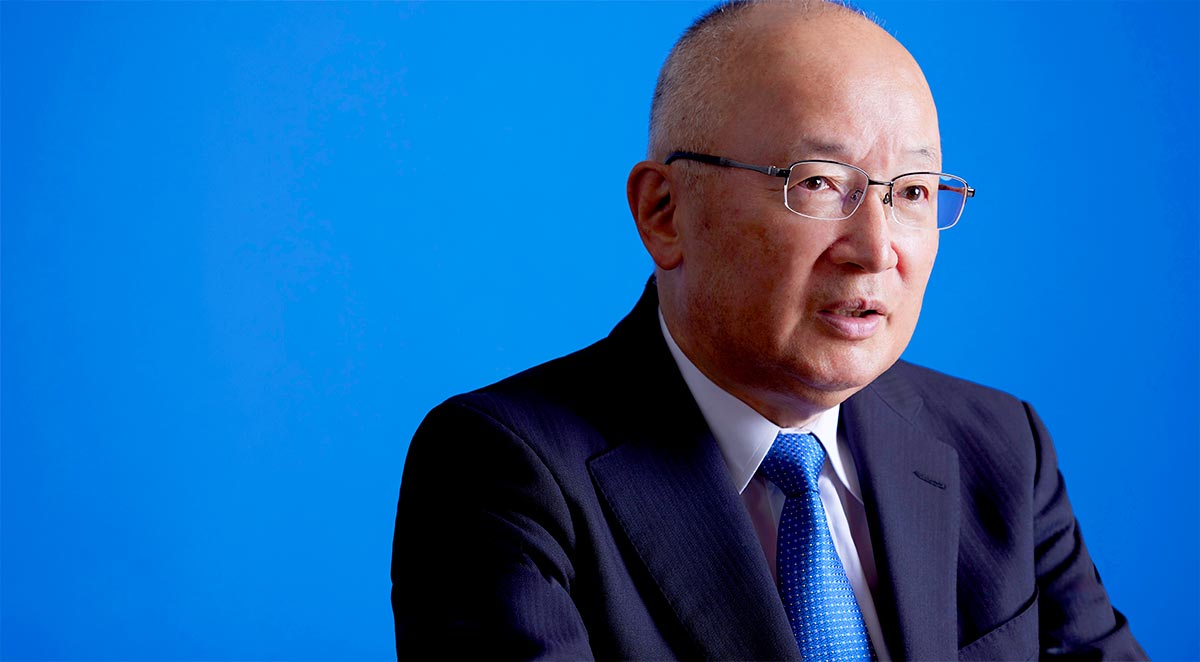
ポートフォリオ戦略においては、安定収益の確保という至上命題のもと、Phase 1ではLNG、ケミカル、海外不動産について事業の拡大に重点を置いています。安定収益型の事業は、日々の積み重ねで少しずつトップラインを押し上げながらボトムラインを改善していくことが重要です。今後はコスト管理を徹底し、収益力を高めていきたいと考えています。成長性が高い、成功確率の高い分野は時代によって変わりますので、将来的には、クルーズ船や自動車物流、または洋上風力発電関連事業で勝負するという可能性もあるわけです。現在注力しているLNG事業も、足元では代替エネルギーがないため、今後も需要が伸びると思いますが、2040~2050年頃までにはピークを迎えることが予測されます。各時流において主力事業を見極め、注力することでグループ全体の成長を持続させる必要があります。
私は、事業を成功させるためには、他者に先んじて動くことが肝であり、勝ち筋を捉えたら、ある程度は思い切って勝負する必要があると考えています。海運業全体として過去数十年間で巨大化し、業界地図も変化してきた中で、勝ち筋を捉えて先んじて動いた者がそのセクターチャンピオンの地位を得ています。私が入社した1980年代には、当社は定期船事業で世界1位、2位を争っていましたが、突然に海外の合従連衡によって巨大コンテナ船時代が訪れ、相対的な地位が下がってしまいました。そうした経験から、私はどうしたら競争に勝てるかを常に考え、他者よりも早く動き、勝ち筋を見定めたら一気に勝負をかけることが重要だと考えています。
Phase 2においては、現在の路線を強化することが基本線となります。その中で、まだ混沌としていてマーケットのリーダーが定まらないような事業分野、例えば洋上風力発電関連事業で、世界での地位を獲れる状況であれば勝負をかけ、勝ち筋が見えなければ事業を撤退するといった見極めも重要になってくるものと思います。
環境戦略について、方針の変更はありません。世界の平均気温は着実に上がり続け、各地で大規模な災害が起こっており、世界全体で気候変動対策に取り組まざるを得ない状況であることは明らかです。特に海運業は、低炭素、脱炭素の燃料に切りかえるという大きな方向性は明確なのですが、代替燃料に様々な選択肢がある中で、単一のソリューションが最適解にはならないという実態が見えてきました。いくつかの選択肢を併存させて海運業全体として脱炭素を図るという全体像が見え始めています。当社はファーストムーバーズの一員であることを標榜していますが、先行することを求めるあまり、突出して後ろがついてこないようなやり方ではだめで、志を同じくする“ムーバーズ”となってトレンドをつくっていく必要があります。
環境対策を行う上で、特に初期投資は多額の資金が必要になるため、一企業だけの力では大規模な拡大は難しく、行政支援が不可欠です。米国、中国、ヨーロッパ、日本の政府などが、最終的にどういった政策をとり、どのセクターに支援するかで方向性が決まる、つまり決断への最終ファクターは経済性よりも政治であるという状況です。そうした背景があり、当社グループではアンモニアやメタノール、水素、そして風力発電等、拡散的に取り組んでいるわけですが、この状況をいつまでも続けるわけにもいきません。今後はグループ全体でのリソース配分を整理し、環境関連においてどの領域に投資の軸を置くのか明確にするステップへ移行したいと考えています。
長期的に信頼され期待される企業グループを目指す

Phase 2における最大の目標は、私たちが現在取り組んでいること、これから挑もうとしていることが実現できるよう組織力・人財力を高めることです。そしてPhase 2の後半には、これまでに積み重ねてきた投資の効果が実現化する見通しであることから、市場における信用度も徐々に高まってくることを期待しています。株式市場から評価を得て、時価総額を上げることができれば、それを梃子に大きなM&Aなど、これまで以上に大きな勝負に打って出ることも可能です。そうした中ではIFRS(国際財務報告基準)への移行プロジェクトを実現することもPhase 2における大きなテーマです。
IFRSへの移行により、グループ全体をグローバル基準に見合った経営体制へと進化させ、世界で成長していきたいと考えています。
株式市場からの評価として、当社の株価純資産倍率(PBR)は2025年3月末で0.67倍となっていました。これは、当社の成長ストーリーへの支持を長期保有志向の機関投資家、個人投資家の皆様から得られていないためと捉えています。
市場からの信頼感を得るためには、株主還元の強化も重要ですが、成長投資の継続と株主還元の拡充を同時に実現していくことが重要です。業績変動が激しい一方で収益性が高く、当社の強みが発揮出来る海運業で競争力を維持し続けるためにも、安定収益の比重を高め、業績を安定させていくことが企業価値を高める上で必要です。
海運業は、継続的に投資をしなければ業界内でのプレゼンスがいつの間にか失われてしまう業界で、極端に高い株主還元へ振り切ってしまうと事業が継続しない宿命にあります。これまでのように極端な好業績と業績悪化を繰り返して、株価も上下するのではなく、安定収益型の比重を増やして毎年コンスタントに2,000~3,000億円、悪くても1,500億円程度の利益を上げながら配当を継続することを積み重ねれば、バリュエーションの修正は必ず起こると思います。市場から評価される5~10年後のバランスシートを考えることもPhase 2での課題です。
こうした長期視点の姿勢に共感し、ご支援いただける機関投資家、個人投資家の皆様を増やしていきたいと考えています。株主還元については、期初時点では、自己資本の充実に伴い、現状の30%から40%に上げていくことを検討していました。しかし、投資家の皆様の声を聞く中で、配当の絶対額を決め、業績が上がっていくにしたがって配当額を引き上げていくことも選択肢の一つと考えており、投資家の皆様から支持される最適な還元政策が何か社内で議論していきます。その中で、徐々にバリュエーションを上げ、長期的にはPBR1倍を超えて1.2~1.5倍の水準に高め、皆様から長期にわたって信頼され、期待される企業を目指していきたいと考えています。
私としては、ここ数年は目指す姿に向けて着実に会社の中身が良くなっていると実感していますので、皆様におかれましては、当社グループの今後にご期待いただきたく存じます。