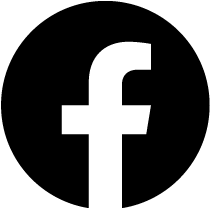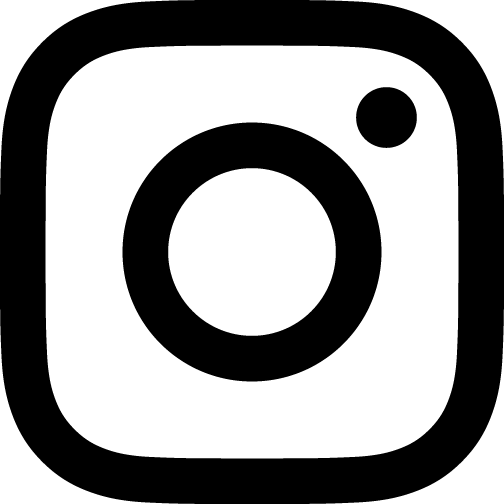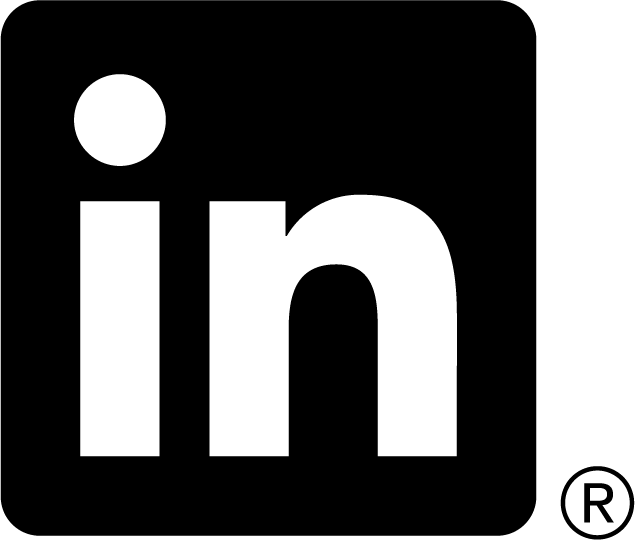- JP
- EN
社外取締役と株主の対話
持続的な企業価値向上を実現するため、当社は適切な意思決定を担保する、実効性のある取締役会を備えています。
当社のガバナンスに関するトピックを中心に、社外取締役が幅広く考えを述べた対話会の様子を紹介します。

2022年度から社外取締役及び取締役会長が主要株主と直接対話し意見交換する「スモールミーティング」を開催しています。2回目となる2024年度では、企業価値の向上、「BLUE ACTION 2035」での戦略、当社が向かう方向性など様々な議論を行いました。5名の機関投資家の皆様による忌憚のない質問に対し、社外取締役4名(2025年2月時点)と池田会長が回答いたしました。
継続的に進化を図る商船三井のガバナンス
野田 私は、取締役会で活発な質問が出ることと、実効的な議論が出来ることは別だと考えています。他の企業では、取締役会において質問が多く、時間をかけたわりに結論に近づいていないというケースがあることも耳にします。実効性向上に向けてどのように取り組まれていますか。
大西 当社におけるガバナンスでは、2021年度に立ち上げたコーポレートガバナンス(CG)審議会が存在することが最も特徴的だと私は考えています。他の企業でも設置されていることもありますが、その多くは予定調和で、コントロールされている場合が多いように感じます。しかし当社の場合は、「ざっくばらんに話せる審議会をつくろう」と池田会長が旗振り役となり、1年をかけてその在り方を議論し作りあげました。各取締役が自由に発言することができる場として設け、気づいたことがあればどのようなことでも発信し、そこで上がった議題について他の委員会で対策を検討するという運用になっています。CG審議会発足当初、他社の経営トップ経験者の方々を招いて、様々な視点から当社における機関設計の変更の必要性を検討しました。取締役会では通常行わないこのような議論はCG審議会だからできたことです。結果として私たちが出した結論は、現状の機関設計のままでまだできることがたくさんあるというものでした。こうして現在の非業務執行社内取締役を置く監査役会設置会社という形態に至っています。このような議論を経てシミュレーションすることができたので、仮に今後、機関設計を変更することになったとしても、不安や抵抗といったものを感じなくなったのではないかと思います。
勝 大西さんが触れられた通り、2022年度に機関設計のあるべき姿を弁護士の方をはじめ外部の専門家に来ていただいて検討し、監査役が独立していることと調査権を有していることが適正なモニタリングを可能にしているという結論に至りました。指名委員会設置会社や、監査等委員会設置会社といった機関設計であっても大型の投資案件になると最終的にはやはり取締役会で審議することになります。当社が業務執行の効率性を高めることを目指している中で、独立性を考えても現状の監査役会設置会社の形が適していると思います。非業務執行社内取締役を置くことで、社内に精通した人が社外取締役と経営陣のつなぎ役として機能していることも商船三井のガバナンスの特徴です。また指名諮問委員会についても、その役割が機能しているものととらえています。現在の橋本社長がCEOに就任される際に、商船三井のCEOはどうあるべきか、必要な資質は何かを徹底的に検討し、今日まで毎年、後継者のリストを更新する形で進展しております。


適正な企業価値評価に向けて実体を伝える
手塚 資本コストや株価を意識した経営の実現について、社外取締役の視点で認識されている課題は何でしょうか。
勝 資本コストや株価を意識した経営について、とりわけ株価純資産倍率(PBR)に関しては取締役会ではこれまで何度も議論を行ってきました。2025年2月時点で当社のPBRは約0.8倍で、株価は上昇傾向にあるものの、1.0倍までには達していません。一方で、2024年10月に発表した1,000億円の自己株式の取得や足元の高い配当性向は株式市場から好意的に評価されているものと捉えています。「BLUE ACTION 2035」のもと、株価を意識した経営がなされており、今後はさらに強調されていくようになると考えています。
大西 海運市況の波は上下ともに大きく激しいという特徴を持っています。そのため、海運業界は過去の実績から見ても、ボラティリティの高い、ハイリスク・ハイリターンな業界であるというご認識をもつ方もいらっしゃるかと思います。そのような業界に身をおきながらも、海運市況が軟調な時であっても利益を安定的に生み出す事業構造を築き上げることを決意し、当社の経営計画である「BLUE ACTION 2035」は作られています。「BLUE ACTION 2035」の戦略に基づいて積極的な投資を実行し、成果も出始めていますが、2024年度は海運市況が好調だったため、現在の当社の実力値が埋もれてしまい、その成果がわかりづらい状況です。不況時ではない今ではその真価が見えづらいのだと考えています。
手塚 現在では「BLUE ACTION 2035」のもとで収益性が向上しているのではあれば、それが投資家に評価されてPBRが1倍を超えているはずだと思います。いまだに過去を払拭できていない理由は何でしょうか。
池田 私たちが「BLUE ACTION 2035」で打ち出したストーリーは、投資家の皆様に好印象を持っていただいているものと認識しています。一方で、ストーリーだけではなく定量的に示すことができないと、投資家の皆様には納得していただけません。各投資案件が本格稼働した折には何らかの方法で定量的に成果をお示しすることが株式市場からのご評価、ひいてはPBRが1.0倍以上になるためには必要だと考えています。
手塚 ROA資本コスト※という形で商船三井らしい事業ポートフォリオのスプレッドを高める戦略を立てていることが「BLUE ACTION 2035」で示されています。その戦略に基づいて下された経営判断によって生み出された安定利益、そして最終的に得られたリターンについては、数年後に提示していただく必要があると思います。現状でも、積極的に投資をされている中で象徴的な具体例をご紹介いただくだけでも十分説得力があると思います。もしくは安定収益型事業や非海運事業の利益がどのように積み上がって事業ポートフォリオの強靭化につながっているか、市況耐性が高まっているかという切り口でも良いと思います。順調に進捗している投資の先に見込んでいるリターンとその安定性へのご説明があれば株価評価の向上につながるのではないでしょうか。商船三井は、世界の海運業と比較しても優れた部分があると私は評価していますので、その情報ギャップを埋めていただきたいと思います。
※ 「BLUE ACTION 2035」では投資によって実現する財務的リターンを、ポートフォリオ別のROAとROA資本コストという手法でも管理しています。
池田 将来的に安定収益に貢献するかという視点から取締役会では投資案件を精査し議論しています。しかしながら、投資したからといって直ちにその成果を財務諸表上で表現できる案件ばかりではありません。多少の時間は要するかと思いますが、分かりやすい形で定量的にお示ししていきたいと考えています。
野田 目に見える形で結果が出るまでには、少し時間がかかるということは理解しています。現時点での進捗や定量的な結果は透明性を持って開示していただくことを求めます。私は、さらにそこに加えて投資家に向けたメッセージを発信されても良いかと思います。「開示可能な情報は全て提示するので投資家が判断してください」ということではなくて、投資家にどのように見てほしいかという発信も効果的だと感じます。
荒川 株価収益率(PER)が今1桁半ばで推移していることが、まさに市況連動型の会社であると見られている証左だと思います。私はPERを継続的に高めていくことにも期待しているのですが、外部からだとどうしてもその時々でどのような具体的なプランを持ち、アクションを起こし、進捗しているのかという実体は見えづらいものです。期待値を高めるためにも、思い描いた姿にどこまで近づいているのかを積極的に発信していただきたいです。ROA資本コストに力点を置いたとしても、PBRが低いままではこれまでと同じ評価になってしまうと思います。安定収益の積み上げ見通しが鮮明になれば、株式市場の見方も変わり、PER2桁の可能性が高まっていくと思われます。




人財が戦略の成功の鍵を握る
平野 安定収益の確保に向けて、商船三井では事業ポートフォリオ変革に取り組まれています。その取り組みにあたっては財務的な観点からのモニタリングも不可欠だと考えます。そのためには取締役会は財務の専門性が高い方で構成されていることも必要だと思いますが、どのようにお考えですか。
大西 財務的な観点は当然ながら必要なスキルセットであると私も考えますが、例えば経営者であれば、財務的な知識は持ち合わせています。財務だけという切り口ではなく、財務的な観点も含めて経営の監督ができることがポイントだと思いますので、そういった人財を取締役会で増やすということは必要だと思います。
柿沼 事業ポートフォリオを変革する中での安定収益型の新規事業への取り組みでは、人財についても重要なテーマだと思います。新しい事業の中での人財やコーポレート部門での強化方針があれば教えてください。
山口 人財戦略については、「BLUE ACTION 2035」での目指す姿と現状とのギャップを埋めるために、どのようなスキルセットの人財が確保できていて、今後はどのような人財が必要となるか、それらをスキルマトリクスとして「見える化」し、明らかにしようとしている段階です。そうした中で、新規事業に取り組める人財についても評価しています。タレントマネジメントシステムを2024年4月から稼働開始しており、基礎的なデータはすでに登録され、グループ各社の要職への登用など一部では活用され始めています。今後は、基礎情報に加えて客観的な評価といった情報も加え、戦略を実行していく上で必要な人財、または最適な人財配置を行うためのプラットフォームを構築しようとしています。
大西 タレントマネジメントシステムは、欧米発祥のシステムで日本では馴染みのない部分もあります。しかしながら当社グループ全体の規模がそこまで大きくないという点は、このシステムに対してポジティブに働く点だと捉えています。現状ではキャリア採用も強化して着実に人財を確保することができています。新たに加わった人財についてもどのようなスキルを持ち、それがどのレベルであるかを把握することは重要であると考えています。
池田 最近では取締役会の中でも、リスクマネジメントの観点からもコーポレート機能を強化しようという議論がなされています。当社の場合、地域戦略のもとで地域組織の強化を図っており、コーポレート機能も日本国内だけではなく、グローバルの視点で検討する必要があります。コーポレート機能を強化するためには、やはり人財が必要で、新規事業に限らず、財務、人事、監査といった分野での専門性が高い人財を確保する必要があります。取締役会の議論を通して、執行側にも重要性が伝播し、当社としての関心ごとの一つとなっています。
山口 地域戦略では、2022年にスタートしたインドでのモデルケースを皮切りに、地域組織の執行体制を強化して事業拡大を実現する取り組みを整備してきました。現在では権限委譲も進み、制度づくりも含めて円滑に進めやすい体制になってきているとは思います。しかし、今はまだ様々な地域で点を打っている段階で、今後はこれらの点をつないでバリューチェーンとして、シナジーを生み出していくフェーズへと進もうとしています。そのためにも人財というのは重要なテーマだと考えています。


ファーストムーバーズとしての揺るがない覚悟
野田 脱炭素社会に向けてファーストムーバーズとなるという宣言をされましたが、米国の政権交代等の影響もあり、世界的に脱炭素への動向がややトーンダウンしているように思います。その中でもファーストムーバーズとしての歩みは止めないのでしょうか。
豊永 私は30~40年ほど前の地球環境問題元年と呼ばれる1989年ごろから地球環境問題に携わってきました。当初は私自身、環境問題については懐疑的に捉えていましたが、環境投資は先に動いたものが勝つことができ、後手に回ると状況はさらに厳しくなるということを経験を通して学びました。環境問題というのは先んじて進めることに価値があるということです。そうした観点から「BLUE ACTION 2035」を見てみると、ファーストムーバーズとしての取り組みは非常に割り切って、先に進むもうとする意思を感じます。これは体面的なものではなくて、自らが率先して先に進むことで中長期的な企業価値に結びつくことを確信しています。この決意は強固なものです。昨今の世界情勢の変化、また今後のエネルギー源がどのように変化するか定まっていないことから、ファーストムーバーズとしての取り組みのペースやスピード感は調整する必要が出てくるかもしれませんが、ゴールに向けての強い意志は揺らいでいないと私は感じています。
勝 取締役会においてはファーストムーバーズへの取り組みと収益性との関係について議論をしています。目先の収益性という意味ではマイナスに振れることもあると思います。しかし、日本からオピニオンリーダーとして世界に対してアピールすることは過去にもあまり例のないことですから、そうした姿勢を全面的に発信していくことは、長期的な観点ではむしろ存在価値が高まるように思います。
野田 私は、ファーストムーバーズであるとことは、素晴らしいことだと感じていましたので、今般の地政学リスクの高まりで決意が揺らいでいるのはないかと心配していましたが安心しました。
山口 ファーストムーバーズとしての目標への方向性は変わりませんが、時間軸や打ち出し方の変化は当然ながらあり得るものと思います。しかしながら、私たちとしてはお客様からのScope 3へのニーズにも応えていかなければいけないという強い使命感を持っています。
池田 執行側の意識としても、ファーストムーバーズとして先頭集団を走る覚悟を持っています。先頭を走るのですが、単独で突破することは望んでいません。マラソンに例えると私たちがトップ集団で走っているとして、トップ集団全体が遅れはじめた際には私たちだけが突っ走るのではなく、引っ張り上げるような意識を常に持っています。私たちだけで成し遂げるというよりは、グローバルに協力関係を築き共にメインストリームを作っていく考えです。
手塚 私たちとしても長い目で見ていますので、ゴールを目指す中でその時々の状況に応じてペースが変わるのは当然だと思います。長期目線での目標は変わらず、舵の切り方を変えるということで理解しました。邦船3社によるコンテナ船事業統合の時から商船三井はムーブメイキングをされてきたので、環境分野に関してもリーダーシップを発揮してくれることを期待しています。それが結果として、商船三井の企業価値向上に結び付くものだと思います。